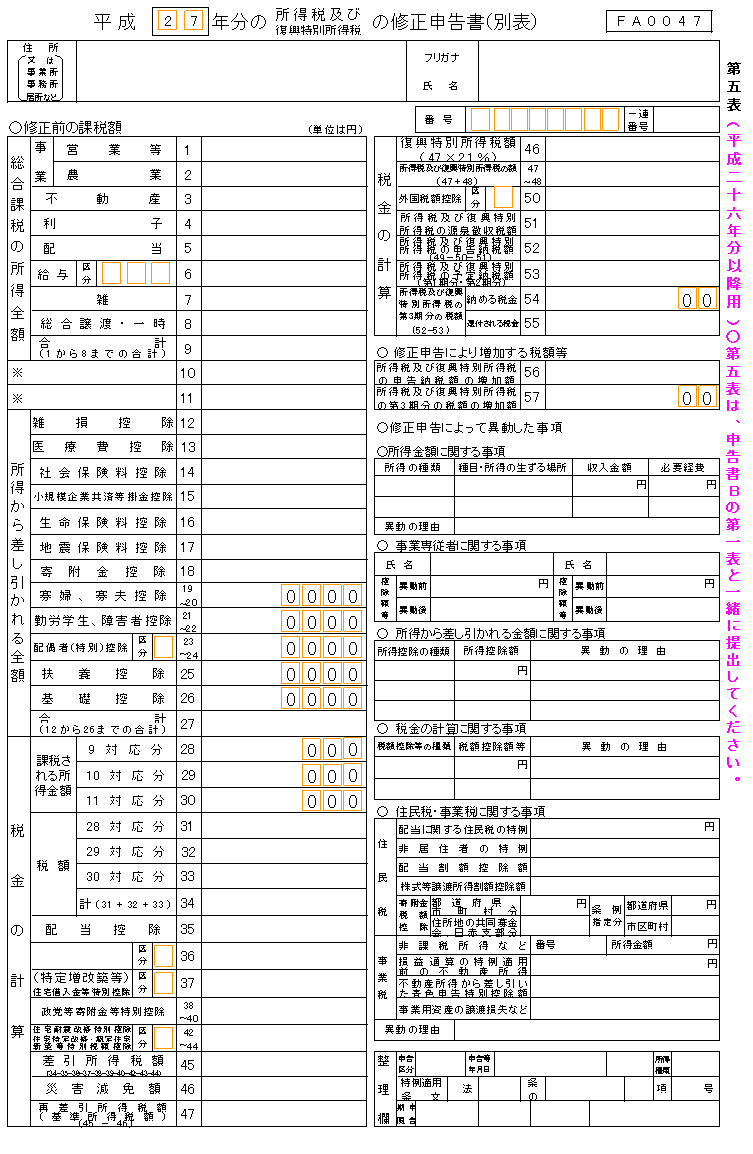申告書の様式・付表・明細書など(申告書は22年より提出用・控用の複写式・・・住民税用は廃止)
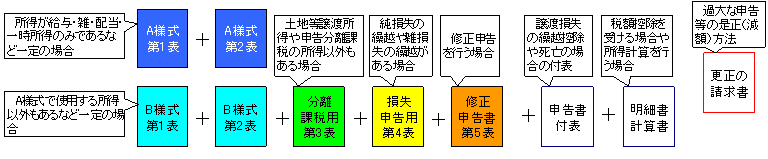
| 所得税の 申告書第一表 | 所得税の確定申告書第二表 | 所得税の 申告書第三表 | 所得税の 申告書第四表(損失申告書) | 所得税の修正申告書(別表) | 更正の請求書 |
|---|
下記は所得税申告書第五表です。
所得税の修正申告書を提出する際に使用する様式です。 税額などが減少する更正の請求はこちら
この様式は、平成26年分以降の年分にも使用できるよう「年分欄」はブランクとなっていますが、同様にブランクであった過年分には何がしかの改正事項があり、実質その年しか使用できないものとなっております。見分け方は右端縦書き「平成26年分以降用」の表示により判断頂きます。
別表となっていますが、通常は当初の確定申告書(この後に修正申告や更正などで数字の異動がある場合は直近の金額)をもとに該当欄に金額を転記します。
修正後の金額は第一表や第三表などで作成をし、修正申告書を提出することで増加する税額は、本表の56、57欄に記載します。第二表の金額に異動がない場合は提出を省くことができます。(第二表は確定申告分を前提に当初から「確定」の文字が印字されています)
修正申告書を提出し、増加(増差)税額を納付書にて納付を終えれば、納税者側からの手続きは一応完了となりますが、次に附帯税が待ち構えています。
まずは加算税、全ての修正申告に対して、賦課されるものではありませんが、増差税額の多寡や自主的な修正申告か、税務署からの指摘によるものかにより加算税(附帯税)の率が異なります。
修正申告の増差税額については、振替納税にて納付することができません、現金納付(署窓口・金融機関窓口)となります。
延滞税(附帯税)についても必ず賦課されるものとは限りませんが、納付が遅れれば遅れるほど日割計算されますので金額は増えてゆきます。修正申告書の提出日から納付日までではなく、申告の法定納期限からの日数計算です。
言い換えれば基本は賦課されますが、一定金額以下は不徴収であります。
当初申告で誤りのない申告を行うことが重要であることは言うまでもありません。しかし、もし申告の誤りに気がつけば出来るだけ早く、それも自主的な修正を行うべきです。附帯税の負担は最小限に。
平成27年分様式の改正事項
特に改訂は見られません。
下記は、「平成 年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書(別表)」様式でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは該当事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では動作を致しません。
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書(別表) 第五表(平成二十六年分以降用)
| 事業所得 | 不動産所得 | 配当所得 | 給与所得 | 公的年金等雑所得 | |
| 雑損控除 | 医療費控除 | 生命保険料控除 | 地震保険料控除 | 寄附金控除 | 所得控除一覧 |
| 税額表 | 配当控除 | 住宅借入金等 | 政党等寄附金 | 耐震改修特別控除 | 住宅特定改修特別税額 |
| 認定住宅 | 外国税額控除 | 専従者給与(控除) | 平均課税 |