平成22年10月、国税庁から表題のとおり所得税の取扱いの変更についての情報が公表されています。
これは、平成22年7月の最高裁判決を受け取扱いの変更を行ったもので、
いわゆる所得区分の変更ではなく、所得計算に関する取扱いの変更となります。(取扱いの変更イメージ図 参照)
所得税では、従来からも表題の年金は雑所得と区分され、総合課税の対象となるものでありました。(平成22年10月国税庁情報)
本稿は、当該情報を基に次の順に掲載しております。
├取扱い変更の経緯
├手続に当たって
├必要な手続き判定表
├よくあるご質問・・・割愛しております。
└用語の説明・・・本文中*印の用語説明
本文中、何頁とある個所については、原文そのままとしており、本稿は単一ページでありますので合致致しません。
この取扱い変更の対象となる方は、「必要な手続き判定表」を参照され、必要な書類を用意頂き、手続をされますように。
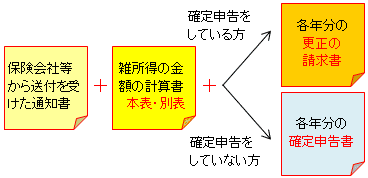
保険会社等から年金等に関する情報を示した「通知書」をご用意頂き、「計算書」の作成、「更正の請求書」又は「確定申告書」の作成をして頂くこととなります。
なお、今回の取扱いにより、「保険契約等に基づく年金の雑所得」を受ける全ての方が、所得税の還付を受ける事が出来る訳ではなく、様々な要因が重なり計算を行ってみなければ判別できません。
計算に使用される計算書及び更正の請求書につにては別ページに掲載をしております。
更正の請求書作成には、確定申告書控も必要でありますが、紛失等最悪の場合、所轄署に申告書の現物が保管されていれば、確認は可能であります。(当初申告後、修正申告や更正がされている場合は、その直近の申告等控)
これから確定申告書を提出される方は、各年分ごとに所得金額が分かる書類、所得から差引かれる所得控除の金額が分かる書類が必要となります。
所得内容や所得控除の種類により、使用する様式に違いがありますので御注意ください。
更正の請求書及び確定申告書の様式については、当事務所所得税申告書様式に掲載しております。
取扱い変更の経緯
この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとしましたので、お知らせします。
これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
お手数をお掛けしますが、このパンフレットの2ページ以降でお手続き方法等をご確認いただき、必要なお手続き(更正の請求*又は確定申告*など)をしていただきますようお願いいたします。
(注1)取扱いの変更の対象となる方については、2ページの「対象となる方」のとおりです。
なお、受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。
(注2)所得税の還付のためのお手続き(更正の請求*又は確定申告*)には期限があります。
詳しくは、3ページの「所得税の還付の手続きの期限」をご覧ください。
(注3)平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付については、現在、特別な制度上の措置が検討されています。
● 取扱い変更のイメージ図(10年間の定期年金の例)
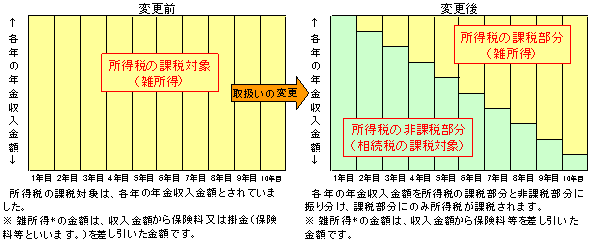
手続に当たって
対象となる方
相続、遺贈*又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給している方が、今回の取扱いの変更の対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
① 死亡保険金を年金形式で受給している方
② 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
③ 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
※ 相続、遺贈*又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権は、相続税法上、相続税や贈与税の課税対象となっています。
なお、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の取扱いの変更の対象となります。
※ 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。
取扱いの変更
受給する保険年金について、次のように取扱いを変更します。
(変更前)各年の保険年金の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税を課税
↓
(変更後)各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます(1ページの「取扱いの変更(イメージ図)」を参照してください。)。
詳しくは、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
なお、国税庁ホームページに、『保険年金の所得金額の計算のためのシステム』(平成22年11月以降ご利用できます。)を用意しておりますので、ご利用ください。
当事務所では、上記システムは掲載しておりませんが、Excelファイルとして計算書を作成しております。
必要な手続き
取扱いの変更の対象となる方には、所得税が還付になるため税務署でのお手続きが必要になる方や、所得税は還付となりませんが住民税や国民健康保険税などが減額となるため市区町村でのお手続きが必要になる方などがいらっしゃいます。
必要となるお手続きを4ページの「必要なお手続き判定表」でご確認ください。
※ 所得税が還付にならない方、住民税や国民健康保険税なども減額にならない方もいらっしゃいます。
所得税の還付の手続きに必要な書類
所得税の還付の手続きとその際に必要な書類は、次のとおりです。
確定申告*をしている年分のお手続き≪更正の請求*≫
・ 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
・ 更正の請求*をする年分の確定申告書の控
※ 確定申告書の控をお持ちでない方は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
・ 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの
確定申告*をしていない年分のお手続き≪確定申告*(還付申告*)≫
申告する内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。
・ 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
・ 給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
・ 社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
・ 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの
所得税の還付の手続きの期限
更正の請求*は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内(注)に行っていただく必要があります。
また、確定申告*(還付申告*)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日(平成17年分は原則として平成22年12月末日)までに行っていただく必要があります。
(注)更正の請求*に基づき減額更正できる期間は、原則として申告書を提出された日から5年間となります。
このため、平成17年分について、早い方は平成22年12月末が期限となりますので、ご注意ください。
お手続きのサポートのご案内
税務署でのお手続き
電話相談・税務署窓口でのご相談
最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
ご用件の番号「0(ゼロ)」を選択いただきますと、今般のお手続き専門の担当者が対応させていただきます。
税務署窓口でのご相談は、皆様をお待たせすることなく丁寧にご説明をするために、お電話等で事前に相談日時等をご予約いただいています。
ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
・電話相談時間:午前8時30分~午後5時(土、日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除きます。)
・税務署の開庁時間:午前8時30分~午後5時(土、日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除きます。)
国税庁ホームページ
国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】の『保険年金の所得金額の計算のためのシステム』(平成22年11月以降ご利用できます。)では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、保険年金に係る雑所得*の金額を計算できますので、ご自宅で『更正の請求書』を作成される場合にはぜひご利用ください。
また、所得税の還付のお手続きに必要な『更正の請求書』や『確定申告書』などの各種様式がダウンロードできます。
市区町村でのお手続き
電話相談・市区町村窓口でのご相談
4ページの「必要なお手続き判定表」により判定した結果、②に該当する場合には、お住まいの市区町村にお電話いただきますと、担当者が対応させていただきます。
窓口での相談をご希望される場合は、相談窓口をご案内します。
※ 引っ越しをされた場合には、転居前にお住まいの市区町村へのお手続きが必要となる場合があります。
当事務所では、上記システムは掲載しておりませんが、Excelファイルとして計算書を作成しております。
必要な手続き判定表
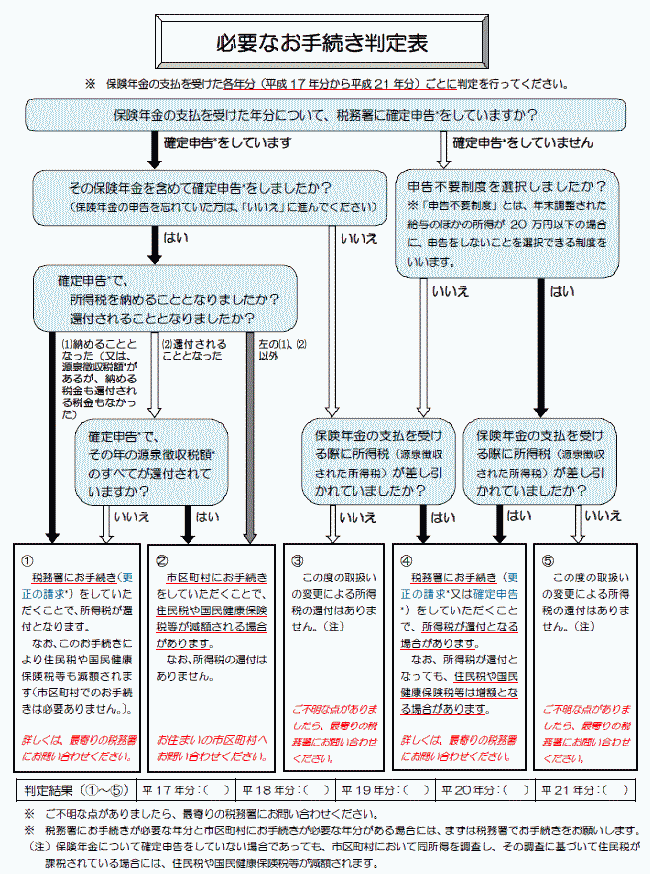
用語の説明
確定申告をした方が、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に、正しい額に訂正することを求める手続きのことです。
◇確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続きです。
◇還付申告
確定申告書を提出する義務のない方でも、源泉徴収税額などが年間の所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
◇雑所得
給不や事業所得など他の所得に当てはまらないような所得で、国民年金などの公的年金や保険年金などが、これに該当します。
◇源泉徴収税額
給不や年金等の支払を受ける際に差し引かれる所得税の額をいいます。
◇遺贈
遺言により被相続人の財産を相続人、相続人以外の方に無償贈与させることをいいます。
