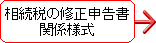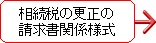一般的に修正申告も更正の請求も、先になされた申告などを是正する方法として、修正申告は増額のため、更正の請求は減額を求めてなされるものになります。
期限後申告とは、申告期限内に当初の申告がなされない状態で、申告期限後に提出されるものであります。
相続税においても、所得税や法人税等と同様に、一定の手続きを経て正しい申告に正されていく訳ですが、相続税に関しては、相続固有の事由から他の税目にないような手続規定も見られます。
修正申告と更正の請求のイメージ※税制改正により、1年という更正の請求期限が5年に、増額更正の場合も5年に改正されています。
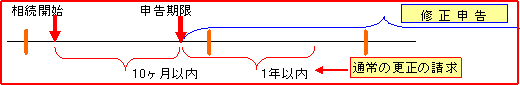
相続税の修正申告書
相続税の申告書の提出、納税等一連の税務手続きが終了後、
先に行った申告の誤り等があり申告内容が過少である場合、納税者自ら若しくは課税庁の調査により誤りを指摘され、正しい申告に改めるために提出する申告が「修正申告書」となります。
この申告により増加した税額に対し、一種の行政制裁である「加算税」や「延滞税」が賦課される事もあります。(脱税と称されるものは併せて刑事罰も課される場合あり)
課税庁とは、通常は相続税の申告書の提出を行った所轄税務署となりますが、
大口の脱漏が見込まれる事案は、場合によっては、国税局の資料調査課や査察部が調査を行う事になります。
また、課税庁は調査に基づく非違事項の是正に応じない場合、納税者側の「修正申告書・期限後申告書」の提出を待たずに「更正や決定」を行う場合もあります。
相続税調査の事例
下記の調査事績は、相続税の申告を必要であるのに、それがなされていなかった無申告事案(期限後申告書の提出)の調査事績は割愛しておりますが、こと税務調査が実施されると、8割強の申告内容に非違があり、かつ大きな「増差」であると感じられます。
「増差」とは、増加した課税価格・税額。「重加算税」とは、仮装隠ぺい行為による加算税。
(参考) 大阪国税局 相続税調査事績 平23.7~24.6
| 調査 事績 |
調査 件数 |
非違 件数 |
非違 割合 |
申告漏れ 相続財産 |
全体 | 現預 金等 |
有価 証券 |
土地 | 追徴 税額 |
本税 | 加算税 | 重加 算税 |
割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,487件 | 2,083件 | 83.8 % |
860億円 | 360億円 | 158億円 | 78億円 | 143億円 | 21億円 | 222件 | 10.7 % |
1件当たりの申告漏れ課税価格は 3,499万円、1件当たりの追徴税額は 661万円
(参考) 全国 相続税調査事績 平23.7~24.6
| 調査 事績 |
13,787 件 |
11,159 件 |
80.9 % |
申告漏れ相続財産 | 3,942 億円 |
1,426 億円 |
631億円 | 630億円 | 追徴 税額 |
649億円 | 107億円 | 1,569 件 |
14.1 % |
|---|
修正申告の内容は、各種相続財産の漏れ・評価誤りや特例適用誤りが原因となることが多いかと思われますが、事実認定の問題ですが、相続税調査においては、被相続人の財産(名義)以外の財産にさえ調査範囲が及ぶことも多々あります。
課税庁在籍当時、様々な事案に対処してきましたが、経験則上も申告漏れ相続財産ベスト3のとおりであった感があります。
また、相続税の特色として、申告後に新たな相続財産が見つかり、その財産を特定の相続人が取得し、取得しない相続人がいる場合でも、その取得しなかった他の相続人にも、新たな相続税の納税が発生する場合があります。
これは、相続税の総額が増加することによる「はね返り」が生じるためであります。
上記のような理由で修正申告書を提出する以外に、相続税では相続固有の特殊な事由により修正申告書を提出する場合があります。
下記更正の請求の特則に掲げる事由のとおり、例えば、期限内申告では未分割のまま、法定相続分で申告を行っていたが、事後、各相続人間の法定相続分と異なる分割が確定、相続税の按分割合が異なれば、当然増額と減額が生じます。
このようなケースでは、加算税等は調査に基づくものではありませんので、原則賦課されません。
相続税の更正の請求書
更正の請求も、一連の税務手続きが終了後、
先に行った申告の誤り等があり申告内容が過大である場合に、納めすぎた税額等を正当な税額等に正すよう、課税庁に対し減額を求める際に提出する手続・書類をいいます。
更正の請求手続き
更正の請求の一般規定は、「国税通則法」に規定され、当該申告書に係る国税の法定申告期限から原則1年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができるとされています。
ただ、原則1年以内であっても、申告期限までに選択が認められている特例等を申告後に選択替えをすることによる「更正の請求」は法令の規定に合致した請求に当たりません。
※税制改正により、上記1年という期限が5年に改正されています。下記法令参照
(参考)当事務所ホームページで、掲載しております各税目に関する「更正の請求書」の解説及び様式は、次からお進みください。
なお、「更正の請求制度」については、税制改正により改正が行われています。
国税通則法第23条1項 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(略)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(略)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
①当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
②略
③第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。
国税通則法第23条2項 納税申告書を提出した者又は第二十五条(決定)の規定による決定(略)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
①その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内
②その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき。 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して2月以内
③その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
更正の請求の特則
更正の請求の一般規定は、上記のとおり国税通則法第23条に規定されていますが、
相続に関しては特殊な事由が発生する事があり、相続税法には、下記のような相続固有の事由によって、過大な申告となった場合の救済規定が設けられています。
この場合、国税通則法の期間制限の規定を盾に門前払いをされることはありません。
・未分割財産の分割により、当初申告の課税価格と異なる場合
・民法規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと
・遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと
・遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと
などがあります。
期限後申告の特則
相続税の申告書の提出期限後に、上記の「更正の請求の特則」により相続人の異動や遺言書の発見などにより、新たに相続税の申告書を提出しなければならなくなった者は、相続税の「期限後申告書」を提出することができます。
通常、期限を徒過した「期限後申告書」は、「無申告加算税」や「延滞税」が賦課されることになりますが、「期限後申告の特則」に該当する期限後申告書を提出した場合は、「無申告加算税」や「延滞税」につき特例があります。
期限後申告と言う言葉だけでは、申告義務を履行していないものと考えられますが、相続という特殊性から、新たに相続人となり期限後申告を行う場合のように納税者の責めに帰せられないようなこともあるためです。